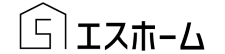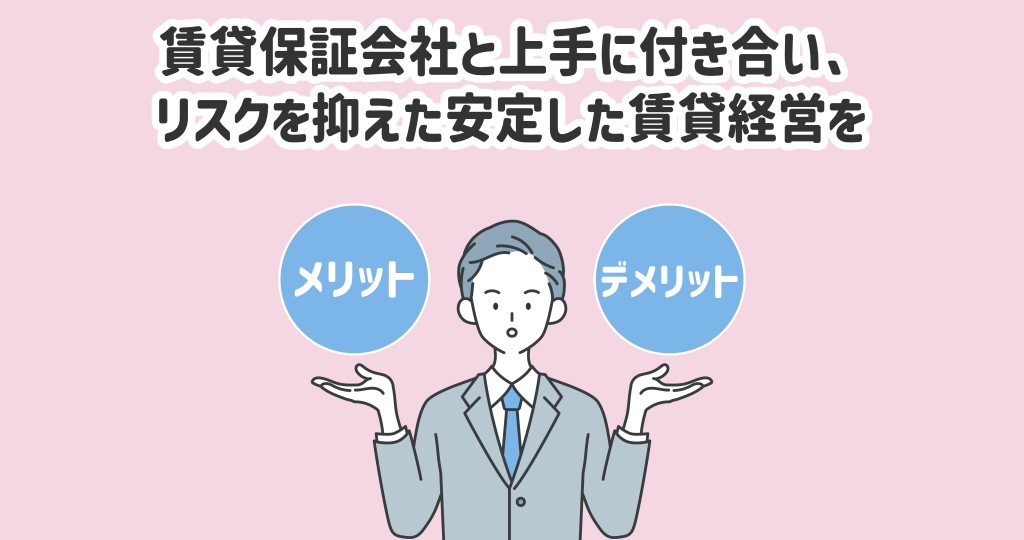浦安市で賃貸物件をお持ちのオーナー様へ。近年、賃貸契約において保証会社の利用が必須となるケースが増えています。保証会社は家賃滞納リスクを軽減する重要な仕組みですが、倒産リスクも存在するため安心して任せるには注意が必要です。
私自身、過去に保証会社が倒産した際、現場で対応に追われた経験があります。その経験から、オーナーとして取るべき備えの重要性を痛感しました。本記事では、保証会社利用の背景、倒産リスク、そしてオーナー様が取るべき具体的対応策を、私の経験した実例を交えて解説します。
浦安で保証会社が必須になった背景
以前は賃貸借契約者が契約中になにかあった際の保証として、連帯保証人を立てて契約するのが一般的でした。ですが保証会社を利用することになった背景として、以下のようなことが理由に挙げられます。
民法改正による連帯保証人制度の変化と影響
これまでの仕組み
従来の契約では、連帯保証人は借主と同様に「無制限の責任」を負わされる仕組みで、一度引き受けたら辞めることもできませんでした。そのため保証人にとっては非常に負担が重いものでした。
2020年の民法改正での変更点
2020年の民法改正により、連帯保証人の保護が強化されました。大きなポイントは、保証の「限度額(上限金額)」を契約時に明記しなければならなくなったことです。これにより保証人は、無制限に責任を負うのではなく、定められた金額の範囲内で責任を持つ仕組みに変わりました。
この改正は保証人保護の観点からは望ましいものですが、いくつかの課題もあります。
金額を具体的に記載する必要がある
例えば家賃滞納から明け渡し完了まで約1年かかった場合、滞納賃料・原状回復費用・残置物の処理費用などを合計すると、家賃の24か月分程度を見込むケースもあります。
家賃10万円なら「240万円」と契約書に記載することになりますが、その金額を前にすると、親族であってもサインを躊躇するケースが少なくありません。
保証人の確保が難しくなる
従来は「きちんと払うから大丈夫」として保証人をお願いできたケースもありましたが、改正後は「万が一のとき最大○百万円を負担してください」と具体的な額が示されます。その結果、借主が保証人を頼みにくくなり、保証人を確保できないケースが増えています。
紹介する不動産会社の手数料収入になる
不動産会社はコンビニの数よりも多いと言われます。またここ10年位は右肩上がりで増加中です。そして実質借りる人(労働人口)は毎年減少。単純に計算すれば1店舗あたりの仲介件数は減少するはずです。
そこで不動産会社は成約1件ごとの利益を上げるため、鍵交換代や消毒料などのオプションを販売して利益を高めています。保証商品もそのオプションの一つで、保証会社を利用する契約では、紹介料が不動産会社に支払われる仕組みがあり、これが普及を後押ししているのです。
管理会社・貸主様にとって手離れが良い
滞納が起きても保証会社に報告するだけで代わりに回収してくれるため、特に管理会社や自主管理している貸主様の負担が大幅に減ります。訴訟や強制執行も保証会社に委任できるので、非常に利便が高く、家賃回収や契約管理のリスクを減らすため、多くの管理会社が保証会社の利用を推奨、あるいは必須としています。
保証会社の倒産リスクとは
2008年、当時業界最大手だった「リプラス社」が倒産しました。
私は当時大手不動産会社の管理部門に所属していましたが、保証商品の知識を買われて対策チームに入り、現場での対応に追われたことをよく覚えています。
リプラス社倒産の背景
リプラス社は賃貸保証業だけでなく、不動産投資などさまざまな事業を展開していました。しかしリーマンショックの影響で投資部門が大きな損失を抱え、資金繰りが行き詰まります。結果として、保証事業で回収した家賃を他部門の穴埋めに使わざるを得なくなり、最終的に家賃の送金が滞って破綻に至りました。
倒産が貸主様に与えた影響
家賃の送金が止まった
リプラス社は借主様から引き落とした家賃を一度自社で預かり、翌月に貸主様へ送金する仕組みをとっていました。倒産時にはすでに引き落とされていた最大2か月分の家賃が、貸主様に送金されないまま消失してしまいました。
滞納の補償が止まった
倒産後に滞納した入居者については補償が受けられず、管理会社様(貸主様)は自ら回収に動かざるを得ませんでした。
保証人無しの契約が続出
リプラス社が保証人の代わりとなっていた契約は、破綻後は保証も保証人もない状態に。一部は後継の保証会社が条件付きで引き継ぎましたが、それまでの間、多くのオーナー様が不安を抱える結果となりました。
賃貸保証会社は倒産のリスクが必ずある
保証会社も民間企業である以上、破綻する可能性をゼロにすることはできません。リプラス社のケースでは幸い家賃保証事業を別会社が引き継ぎ、多くの契約が継続されましたが(条件付きでしたが)、次に同じことが起きたときにうまく承継される保証はありません。
特に現在は賃貸借契約のほぼすべてで保証会社が利用されているため、もし大手保証会社が破綻すれば当時以上の混乱が起きる可能性も十分に考えられます。
また昨今では物価上昇による生活コスト増が、賃金上昇が上回らず実質賃金が低下しており、滞納率も上昇する可能性があり、滞納率の上昇は保証会社の運営に暗い影を落とします。
私が考える、上手な賃貸保証会社との付き合い方
賃貸保証会社は今や大切なパートナーです。しかし、すべてを任せきりにしてしまうのは危険です。以下のような視点で上手に活用してください。
保証会社の財務内容や実績を確認する
インターネットで検索すると、保証会社は財務諸表や取引状況などを開示してるところも多く、きちんと運営されているか判断する一つの指標になります。危険性を事前に把握できれば、利用を控えたりなど対策を打つことが出来ます。
保証会社を分散する
不動産会社によっては、保証会社複数と契約できるところも多く有ります。1社に偏らず、複数社の保証商品を利用することで、倒産リスクを分散させるのも1つの手です。
また保証会社必須ではなく、例えば学生などの滞納率が低いと思われる層には連帯保証人をつけての契約にするなど、保証会社の利用自体を柔軟にするということも検討してみてはいかがでしょうか。
家賃の保全方法に注意する
保証商品の家賃の流れには、大きく以下の3つのタイプが有ります。
- 借主口座から家賃が引き落とされ、保証会社の口座で管理されるタイプ
- 借主口座から家賃が引き落とされ、信託口座で分別管理するタイプ
- 家賃を保証会社に通さず直接オーナー様口座へ入金するタイプ
①の場合で保証会社が倒産してしまった場合、家賃は他の財産と一緒に破産管財人の精算後でしか返還されませんが、②か③の場合は家賃全額が貸主様の口座に入金されます。
もし商品を選択できるのであれば②か③の商品を使用したいと不動産会社へ伝えてみましょう。
契約書に保証会社利用の追加条項を加える
保証会社が倒産した場合に備え、保証会社を利用する際は「連帯保証人を追加するか新たな保証商品へ借主負担で加入する」という一文を入れることも検討しましょう。ただし、実際に倒産した際に連帯保証人になってくれる人がおらず、新しい保証会社の審査が落ちてしまったとしても、そのことだけを理由に契約を終わらせることは出来ないので注意が必要です。
貸主様自身での入居審査もお忘れなく
保証会社の審査をパスしたからといって安心しきらず、「この人は家賃を継続的に支払えるのか」という視点でご自身でも確認していただけると、ダブルチェック・トリプルチェックとなり安全な賃貸経営につながります。
最後に 〜うまく賃貸経営のリスクを低減するために〜
保証会社の存在は、現代の賃貸経営においてとても重要です。しかし一方で「保証会社も企業であり倒産しうる」という事実を忘れてはなりません。
賃貸保証会社の仕組みを正しく理解し、メリットとデメリットを見極めながら、上手に活用していくことで、貸主様にとって安心できる賃貸経営を続けていただければ幸いです。