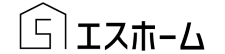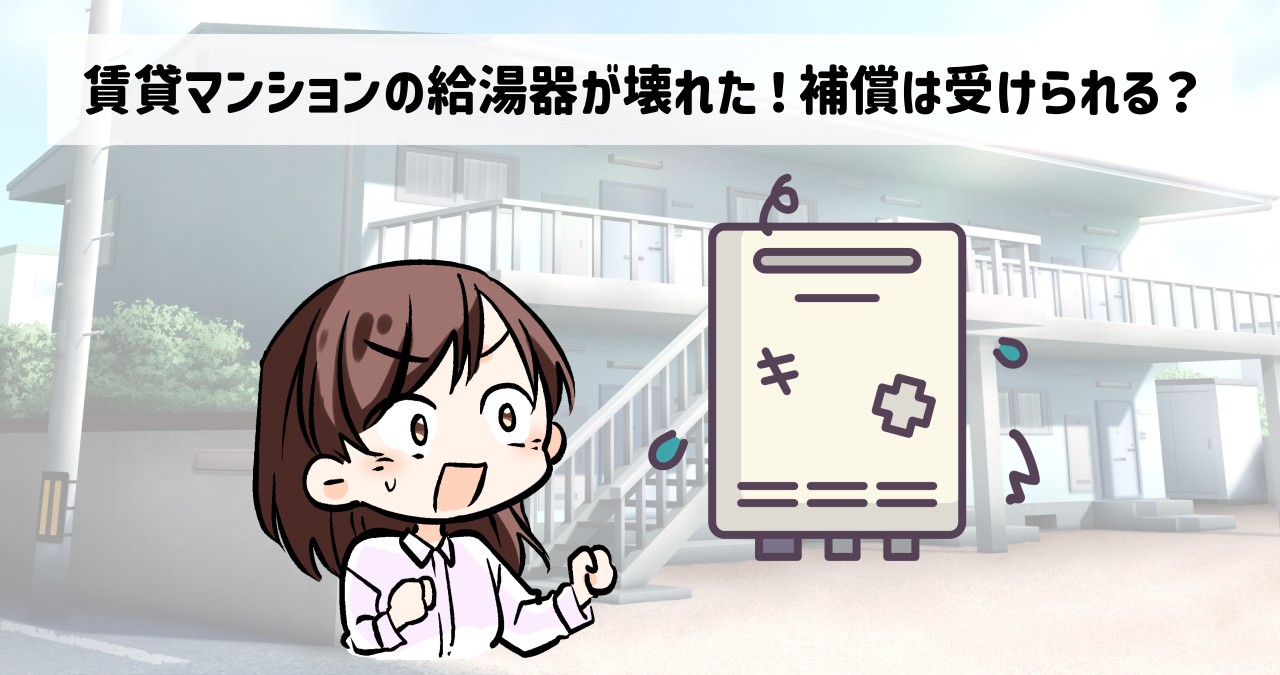突然のお湯トラブル、どうする?
給湯器の故障は、日々の生活に大きな影響を与えます。特に寒い時期にお湯が使えないと、不便どころでは済みません。そんなとき、修理が終わるまでの間の不便さに対して何らかの補償は受けられるのでしょうか?また、修理費用は誰が負担するのか?
この記事では、給湯器が故障したときの対応方法や補償の可能性について分かりやすく解説します。
給湯器の修理費用、誰が払う?
まず、故障した給湯器の修理費は誰の負担になるのかを確認しましょう。
(1) 基本的には貸主(オーナー)が負担
給湯器は物件の設備の一部なので、通常は貸主(オーナー)が修理費を負担します。賃貸契約では、物件の維持管理責任が貸主側にあることが多いからです。
(2) 借主(入居者)が負担するケースも
ただし、以下のようなケースでは入居者側が負担しなければならない可能性があります。
- 誤った使い方による故障(無理な操作やメンテナンス不足)
- 経年劣化ではなく、入居者の過失で故障したと判断される場合
例えばお掃除中に誤って操作パネルを割ってしまい、給湯器が使えなくなってしまった場合などは、入居者の過失のため修理費用を負担しなければなりません。
お湯が使えなかった期間、補償は受けられる?
では給湯器が壊れた場合、家賃の減額や補償を受けられる可能性はあるのでしょうか?
(1) 民法上の「賃料減額請求権」について
民法第611条では、「賃貸物件に不具合があり、通常通り使えない場合は、その程度に応じて賃料を減額できる」と規定されています。給湯器が壊れてお湯が出ない状況が長期間続く場合、この条文を根拠に家賃の減額を交渉できる可能性があります。
(2) 補償が受けられるかは状況次第
実際に補償が受けられるかどうかは、次の要素によって変わります。
- 故障期間の長さ(1〜2日程度では補償が認められにくいが、1週間以上なら交渉しやすい)
- 代替手段の有無(例えば、浴室の給湯が使えなくても、キッチンのお湯が使える場合は減額の可能性が低くなる)
- 貸主や管理会社の対応(修理対応が遅れた場合は交渉の余地がある)
実際の賃貸契約では「給湯器の故障による家賃減額」が明記されていないことが多いため、補償を受けるには交渉が必要です。
家賃減額や補償を受けるためのポイント
家賃減額や補償の具体的なステップ
家賃減額や補償を希望する場合、以下のステップで対応しましょう。
- すぐに管理会社・大家へ連絡
- 給湯器の故障を報告し、修理の日程を確認。
- 連絡した日時や内容を記録しておく。
- 修理完了までの期間を記録
- 何日間お湯が使えなかったかをメモ。
- 可能なら、管理会社からの対応記録(メールや書面)を保存。
- 補償の根拠を整理し、交渉する
- 民法611条をもとに家賃減額を相談。
- 代替手段がなく、実際に生活に支障が出たことを伝える。
※参考資料
公益社団法人日本賃貸住宅管理協会にて、貸室や設備のトラブルによって通常住める状態のお部屋でなくなった場合の賃料減額の目安が
として発表されています。法的拘束力はなく、あくまで指標となるものですが、近年の判例も盛り込まれているので一つの基準になるかと思います。もしどれくらいの請求が妥当であるのか迷われる場合にはぜひ参考になさってください。
修理までの間にできること
給湯器が直るまでの間、お湯が使えない状況をどう乗り切るか考えましょう。
- 銭湯やスポーツジム、漫画喫茶などのシャワーを利用
- 近くに公共浴場があれば、一時的な対策として活用。
- 管理会社に代替措置を相談
- 長期間修理ができない場合、仮住まいの提供などの対応を求めるケースも。
6. まとめ
- 給湯器の修理費は基本的に大家(貸主)が負担。
- お湯が使えなかった期間の補償はケースバイケースで、交渉が必要。
- 補償を受けるには、迅速な連絡・記録・交渉がポイント。
- 修理完了までの間、代替手段を考えて生活の不便を最小限に。
給湯器のトラブルが発生したら、まずは冷静に管理会社へ連絡し、適切な対応を求めることが大切です。いざというときに困らないよう、契約内容や対応方法を事前にチェックしておきましょう。
ちなみに、千葉県浦安市で賃貸アパート・マンションを管理している当社では、給湯器のトラブルが発生した場合、家賃減額や補償を受けるためのポイントの参考資料でお示しした「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」の「ガスが使えない場合」を参考に、貸主様・借主様へご説明し、ご了承を頂いています。公的な期間が発表している資料には判例を元にした根拠や具体性があるので、もしトラブルに発展しそうな場合は参考にされてみてはいかがでしょうか。